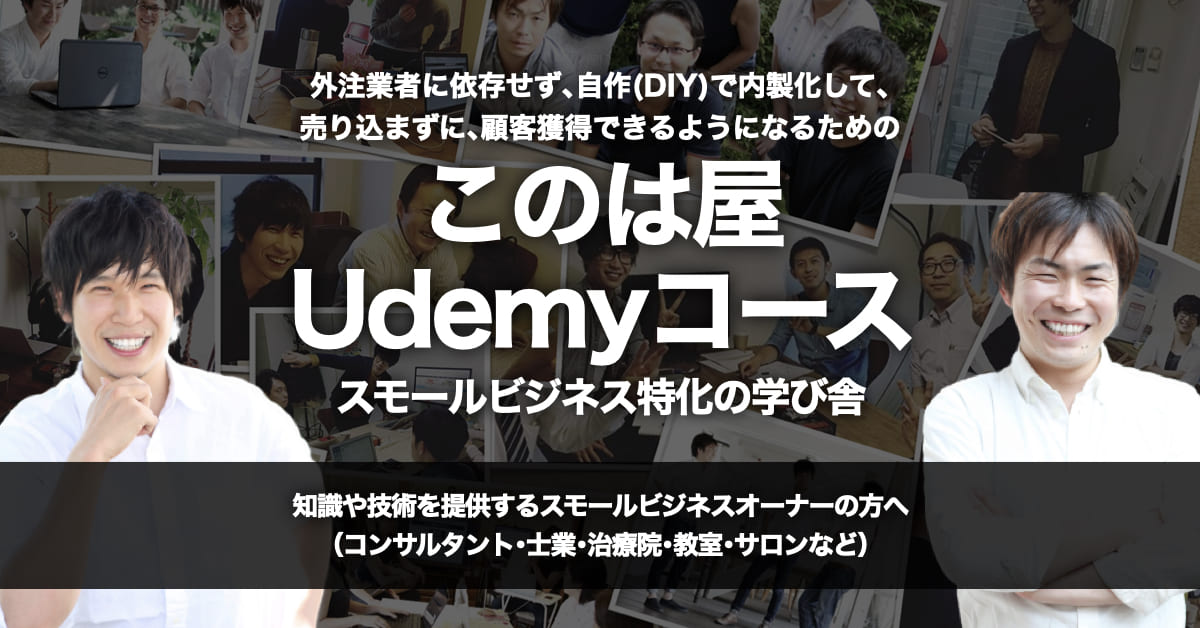寺子屋といえば、江戸時代の学校ですね。
「手習い」とも、呼ばれたそうです。
現代の子どもは、6歳頃に小学校に通い始めます。
寺子屋には、何種類の教科書があった?
江戸時代の子どもは5歳〜8歳頃に、寺子屋に通ったそうです。
寺子屋は学校ですから、教科書があります。
ではこの教科書が、何種類あったと思うでしょうか?
ちょっと、想像してみてください。
5種類?10種類?20種類?
- 5種類?
- 10種類?
- それとも、20種類?
いえ、違います。
なんと、7,000種類もあったといいます。
そんなにいる?
「7,000」です。
とてつもない数ですよね。
「そんなにいる?」と、思うかもしれません。
ではなぜ、7,000種類もの教科書があったのでしょうか?
最も適した教育をするため
それは、
- 地域や職業
- 子どものレベルごと
に、最も適した教育をするためなのだそうです。
江戸下町の商人の教育
たとえば、江戸下町の商人が多い地域。
ここでは「商売往来」を使い、職業の知識を教えたといいます。
子どもたちは、
- 商売に使う用語や単位
- 商売の心得
などを、学んだわけです。
机を並べていなかった?
また学校というと、
「机を並べて、生徒全員が先生の方を向く」
というイメージがありますね。
ですが、寺子屋では
「ひとりひとりが、それぞれ違う方向を向いていた」
そうです。
画一的な教育ではない
教える内容が、画一的では無かった。
ですから、先生(手習い師匠)は、ひとりひとりに適した内容を教えていたのです。
そのため、机が同じ方向を向いている必要は、ありませんでした。
ひとりひとりに適した教育
こんな風にして、寺子屋では、
- 画一的な教育ではなく、
- ひとりひとりに適した教育
をおこなっていました。
ここから、現代の商売が学べることがあります。
みんなと同じことをしていないか?
商売について、学べば学ぶほど、画一的になっていきます。
要するに、
「みんなで、同じことをするようになる」
ということです。
たとえば、ブログ集客を例に取ってみましょう。
ブログ集客の例
スモールビジネスであれば、「ブログをやった方が良い」とよく言われるでしょう。
言うまでもありませんが、
- ブログ集客コンサルタント
- ブログ集客代行業者
- …etc
は、「ブログがおすすめ」と言います。
当たり前ですね。
彼らはそれで、食っているのですから。
集客手段は、ブログだけじゃない
でもブログを書くのが、得意じゃない人もいます。
そんな人は、無理してブログをやらなくても、良いのです。
だって、集客手段は、ブログだけじゃないから。
打つ手なんて他に、いくらでもある
打つ手なんて他に、いくらでもあります。
- YouTube
- メルマガ
- リスティング広告
- ディスプレイ広告
- Facebook広告
- …etc
みんなと同じ < 自分に適したこと
大切なのは、
- 「みんなと同じことをする」
- ではなく、
- 「自分に適したことをする」
ということです。
ひとりひとりに、適した手段
なぜ寺子屋には、7,000種類もの教科書があったのでしょうか?
そう。
ひとりひとりに、適した教育を行なうためです。
現代の商売も、同じこと。
「みんながやっている」なんて関係ない
「みんなが、ブログをやっている」
だからといって、あなたがブログをやらなきゃいけないわけではありません。
- 話すのが得意なら、YouTubeをやれば良い
- 交流が得意なら、Facebookをやれば良い
- …etc
オンラインに限らない
もっといえば、パソコンが苦手なら、
- 異業種交流会に、行く
- 打ち上げや飲み会に、参加する
- …etc
オフラインで、人付き合いに、力を入れれば良い。
自分に適したことをする
大切なことは、自分に適したことをするということです。
- 自分は、どんなことが得意なのか
- どんなことが、最も適しているのか
今一度、じっくりと考えてみてください。
書籍を参考にしてみても、良いかもしれませんね。
編集後記
ブログ記事が書けないからといって、
「ウェブから集客することができない…」
なんて、考える必要はありません。
もしコンサルタント先生に依頼するなら、
- 「ブログ”だけ”が正解です」
- という人ではなく、
- 「ブログ”も”おすすめです」
という人を、選びましょう。
「これだけが正解」なんてものは、ありません。