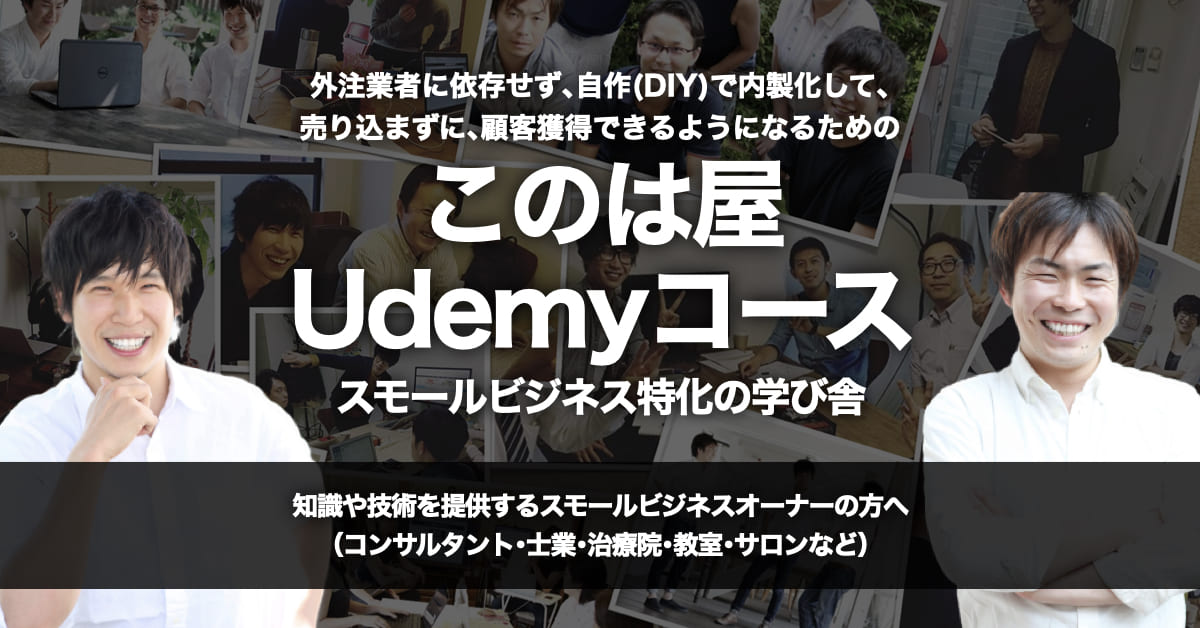セミナーを開催して、そこで商品を売る。
このような、営業を行っている人は、多いでしょう。
- セミナーから、個別面談に誘導
- セミナーで、塾や講座を販売
セミナーを「体験の場」として用意し、そこで信頼を獲得する。
スモールビジネスにとっても、セミナーは、有効な手段の1つです。
いきなりは買わない
いきなりは購入しないけど、セミナーがあれば、参加したい。
顧客心理から考えて、このようなニーズがあります。
そういう意味で、セミナーは、理にかなった営業スタイルと言えるでしょう。
セミナーでの営業方法に関する書籍も出版されています。
実際に、このは屋も実践しました
実は我々このは屋でも、セミナー営業を実践しています。
セミナーを通して、たくさんの方に関わることができました。
おかげさまで…
決して安くない高価格サービスを、多くの方に購入していただけるようになりました。
ぜひ、教えて下さい
すると、
「ぜひ、そのセミナーのやり方を教えてほしい」
という声も多数いただきました。
なので今回は、「セミナー営業のコツ」お伝えします。
セミナー撮影屋時代
我々は以前、セミナー撮影業を営んでいました。
- 講師
- コンサルタント
- 士業
- カウンセラー
- …etc
といった、ノウハウを持っている専門家向けのサービスです。
撮影→マーケティング支援
- セミナーを撮影して、
- セミナー運営のサポートも行い、
- マーケティング支援もする
というサービスを提供していました。
セミナー撮影で得た、気づき
ある日、いつも通りセミナーを撮影していると…
講師の方が、最後に言うんです。
「◯◯というサービスに興味がある方はお申し込み下さい〜」
平気な顔して、50万円以上の商品・サービスを売りさばきました。
セミナーなら、高額商品でも売れる!
我々は、運営のサポートもしていたので、申込用紙も管理していました。
なので、リアルな申込み者数も分かってしまいます。
売れている人は、売れるんです。
逆に、売れない人は全く売れません。
(この時、結構気まずかったりしますw)
その両者に、話すスキルの差、プレゼンスキルの差は見られません。
「なんでだろう?」と思っていました。
売れる・売れないの明確な違い
さすがに、山ほどのセミナーに関わってくると、その理由が分かってきます。
モノが売れるセミナーと、モノが売れないセミナー。
両者には、「明確な違い」がある。
モノが売れているセミナーには、例外なく「共通点」があるということ。
これがわかった時、「この仕事をしててよかった」と思いました(笑)。
売れるセミナーの共通点
そこから、独自に「セミナー研究シート」の作成に着手し始めます。
成功しているセミナーを、仔細に眺めて、研究。
それはもうオタクのように、探求しました。
その結果、ある「答え」にたどり着いたんです。
それは…
売れるセミナーには、「型」があるということ。
2つの分類
そして、この型には2つの分類があります。
- セミナーのシナリオ
- セールスパッケージ
この2つ両方を意識していなければ、セミナーはうまくいかないんです。
どちらか片方では駄目。2つの型が必要なんです。
セミナーのシナリオ
シナリオは、セミナーの「台本」です。
ここを、とにかく練る必要があります。
単に、情報提供するシナリオでは売れません。
では、どんなシナリオなら売れるか…。
シナリオ=教育
ポイントとして、
参加者を「教育」するような、シナリオである必要があります。
教育を行い、次の商品の必要性を高めるんです。
それがなければ、お客さんは次に進んでくれませんからね。
シナリオが200点でも売れない
ところが、シナリオばかりに、気を取られてはいけません。
200点のシナリオを作っても、成約率が10%未満。
そんな方を、たくさん見てきました。
なぜ、そんなことが起きるのでしょうか。
それは、「セールスパッケージ」が無いからなんです。
セールスパーケージが必要
セミナーで大切なのは、
「何を話すか」ではなく、「誰に話すか」です。
つまり、見込みの濃いターゲットを集めて、教育するステップが不可欠です。
完璧なセミナー台本を用意しても、聞く人が適切でなければ、売れません。
セールスパッケージとは、「集客の仕組み」です。
セミナー営業の正しい4ステップ
セミナーの正しいやり方は、下記の流れです。
- セミナーに興味がある人を、集める
- セミナーを案内する
- セミナーで教育する
- 説明会、面談でクロージング
これが、定石。
こうした集客のパッケージを用意して初めて、セミナー営業は成功します。
見落としがちなポイント
多くの方は、ファーストステップの、
「セミナーに興味があるであろう人をまずは集める」
の部分を見落としています。
この部分は、セミナーの内容よりも、10倍大切です。
このあたりは、書籍を参考にしても良いでしょう。
見込み客はいるのか
こうした人たちを、「見込み客」と呼びます。
あなたのセミナーに興味ありそうな、「見込み客」はいますか?
まずは、そこからです。
正しい見込み客に売れば、自然と高確率で売れます。
編集後記
セミナーというと、ついつい、
- シナリオ作成や
- スピーキングスキル
- プレゼンテクニック
などに目が行きがちですが、それは二の次です。
「集客の仕組み」を、しっかり持ってからでも、遅くはありません。
取り組む順番に、注意しましょう。