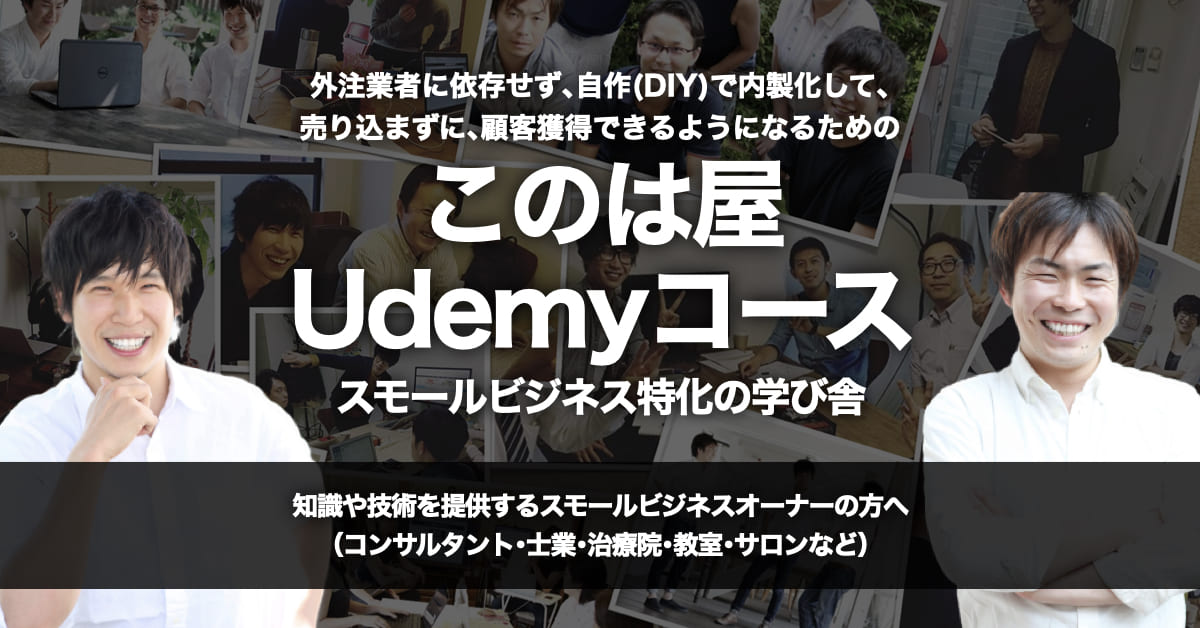ランディングページとは、どんなページでしょうか?
「広告からの飛び先ページ」だけを、指すのではありません。
では、ランディングページとは、どんなページのことをいうのでしょうか?
ランディングページとは?
「ランディングページ」という用語を、聞いたとき。
まず浮かぶのは、
- どんなページ?
- サイトと何が違うの?
という疑問では、ないでしょうか?
着陸するページ
そもそもランディングページは、英語で「Landing Page」と書きます。
- 「Landing」は「上陸、着陸」
- 「Page」は、そのままページ
といった、意味です。
つまり、「着陸するページ」ということですね。
どこから着陸する?
飛行機は、「空」から着陸します。
では、ユーザーはどこから着陸するのでしょうか?
結論からいうと、「リンク」からです。
リンクをクリックした後に、表示されるページ。
すべてを、ランディングページといいます。
Yahoo!を例に取ってみる
例えば、Yahoo!のトップページを見てみましょう。
ヤフーニュースをはじめ、色々なサイトへのリンクがありますね。
このリンクを、クリックしたとします。
すると、
- ニュースサイトの記事
- ブログの記事
などに飛びます。
すべてランディングページ
これらすべてが、ランディングページです。
- 「ニュースサイトの記事やブログの記事」
- =「Yahoo!からのランディングページ」
というわけです。
飛行機は、空から。ユーザーは、リンクから。
難しくありませんね。
- 飛行機は、「空」から着陸する
- ユーザーは、「リンク」から着陸する
ということです。
なぜ広告と一緒に聞くことが多いのか?
でも、ランディングページという用語は、
- Google広告
- Yahoo!広告
- Facebook広告
- …etc
などと、一緒に聞くことが多いですよね。
なぜなのでしょうか?
区別が付かなくなってしまう
仮にリンク先ページを、すべてランディングページと呼んでいたとします。
すると、サイトやページとの区別が付かなくなってしまいます。
ですから、ランディングページは、
- Google広告
- Yahoo!広告
- Facebook広告
- …etc
などと共に、聞くことが多いのです。
縦に、ズラーっと長いページ
ランディングページとは、広告からの飛び先ページである。
といわれても、あまりピンと来ないかもしれません。
「縦に、ズラーっと長いページ」といえば、分かるかもしれませんね。
あのページが、ランディングページです。
「はいはい、あのページのことね」
おそらく、今までに見たことがあるかと思います。
「はいはい、あのページのことね」といった感じかもしれませんね。
あのページが、ランディングページです。
ランディングページの種類
大まかに、ランディングページについて理解できたでしょうか。
それでは、より具体的に、みていきましょう。
ランディングページの、種類についてです。
役割ごとに、大きく3つの種類に分けることができます。
(1)通常の意味のランディングページ(サイト・ブログ等)
まずはじめに、通常のランディングページです。
一番はじめに、お伝えしたものですね。
「ユーザーが、リンクをクリックして、訪れたページすべてのこと」です。
- ニュースサイト
- ブログ記事
など、様々なページを含みます。
ですので、特に決められた役割はありません。
用語の意味での、ランディングページです。
(2)メルマガ&資料請求用ランディングページ
次に、「メルマガ&資料請求用ランディングページ」です。
ランディングページの中でも、
- メールマガジンの登録
- 資料の請求
- …etc
を、目的とするページのことですね。
「無料」の案内ページ
要するに、商品やサービスの販売など、
- 「有料」の案内ではなく、
- 「無料」の案内ページ
ということです。
オプトイン、リード獲得…
ちなみに、メルマガ&資料請求用ランディングページのことを、
- オプトインページ
- リード獲得ページ
などと、呼びます。
(3)商品・サービス販売用ランディングページ
最後に、「商品・サービス販売用ランディングページ」です。
メルマガ&資料請求用ランディングページとの違い。
それは、「有料」の商品やサービスを案内するということです。
一番イメージしやすい、ランディングページですね。
なぜランディングページを制作する必要があるのか?
さて、ランディングページの概要と種類についてみてきました。
ここで、そもそも「なぜランディングページを制作する必要があるのか?」
その理由について、確認していきましょう。
答え:ユーザーを迷わせないため
ランディングページを制作する理由は、「ユーザーを迷わせないため」。
この一点に、尽きます。
サイトやブログを訪れたユーザーが、取る行動。
通常それは、明確に定まったものではありません。
ユーザーの行動の選択肢は多数ある
サイトを訪れたユーザーは、
- 会社概要ページをみる
- 代表プロフィールをみる
- アクセスマップを確認する
などの、行動をしますね。
ブログを訪れたユーザーは、
- 記事を読む
- 関連記事を探す
- お問合せをする
などの行動をします。
ランディングページは、2つだけ
共通しているのは、「行動の選択肢が、多数ある」ということです。
ランディングページは、違います。
ユーザーが取る行動というのは、2つしかありません。
- 申し込む
- 申し込まない
いずれかのみです。
「申し込む」か「申し込まない」
それは、
- メルマガ&資料請求用ランディングページ
- 商品・サービス販売用ランディングページ
いずれでも、一緒です。
選択肢があると迷ってしまう
つまり、ユーザーは、迷う必要がありません。
ウェブ上に限らず、人は複数の選択肢があると、行動に迷いが生じます。
サイトやブログでは、ユーザーにとって「行動の選択肢」がたくさんあります。
ですので、迷ってしまいます。
ランディングページは、選択肢が2つしか無いので、迷いません。
この事実は、特に広告を出稿する際には重要となります。
広告出稿主の目的は?
広告出稿主の目的は、何でしょうか。
それは、ユーザーから「申込み」(以下、コンバージョン)を獲得することです。
- メルマガの登録
- 資料請求
- 商品・サービスの販売
いずれにしても、コンバージョンを得たい。
だから、わざわざお金を出して、ページを広告に出すわけです。
もう一つの目的
コンバージョンを、獲得する。
それに加えて、実は、もう一つ目的があります。
それは、「コンバージョンを獲得しない」という目的です。
コンバージョンを獲得しない
コンバージョンを獲得するために、広告出稿するんじゃないの?
と思いますよね。
要するに、
- 自社の属性に合わないユーザー
- 自社の商品やサービスでは満足させてあげることのできないユーザー
からは、コンバージョンを獲得しないということです。
コンバージョンを獲得しない?
- 不要なクレーム
- 過剰な約束(オーバープロミス)
を避けるためには、コンバージョンを獲得しないということも、大切になってきます。
これが、「行動の選択肢」が明確ではない、サイトやブログだと難しいのです。
その点、ランディングページであれば、選択肢が明確に2つしかありません。
ですので、ユーザーを迷わせることはありません。
双方にメリットがある
つまり、「行動の選択肢」が明確というのは、
- 広告出稿主
- ユーザー
双方に、メリットがあるわけです。
特に大切なのは、「ユーザーに、メリットがある」ということですね。
また、ランディングページを制作するメリットは、広告だけに留まりません。
有料集客と無料集客
- Google広告
- Yahoo!広告
- Facebook広告
- …etc
これらを、「有料集客」と呼ぶならば、
- ブログ
- YouTube
- 各種SNS
は、「無料集客」ということになります。
- 記事を更新する
- 動画をアップロードする
- SNSに投稿する
上記自体に、費用は発生しませんからね。
自社のことを見つけてもらう
ユーザーに、自社のことを見つけてもらう。
そのためには、広告を出稿することに加えて、
- ブログ
- YouTube
- 各種SNS
を更新することも、大切です。
ただ闇雲に更新していても…
ですが、ただ闇雲に更新していても、売上には結びつきません。
- ブログのPV
- YouTubeの再生回数
- SNSのフォロワー数
が上がっても、肝心の「申込みページ」が無い。
そうなると、ユーザーはそのまま去ることになってしまいます。
ランディングページは、必須
ランディングページがあれば、
- ブログ
- YouTube
- 各種SNS
を見たユーザーに、
- 自社のメルマガ
- 商品・サービス
- …etc
を、案内することができます。
つまり、
- 広告で、有料集客する
- ブログやYouTubeで、無料集客する
いずれにしても、ランディングページは必須ということです。
ランディングページを制作する4つの方法
それでは、
「実際に、ランディングページを制作する方法」
について、みていきましょう。
- 外注
- 自作
の、大きく2つ。
それぞれにまた2つ、合計4つの方法をご紹介します。
(1)外注
まずは、外注して、ランディングページを制作してもらう方法です。
- 「制作業者」に依頼するパターン
- 「クラウドソーシングサイト」で依頼するパターン
の2つの方法が、あります。
(1-1)制作業者
最も、一般的な方法となります。
検索エンジンで、
「ランディングページ 制作」
と検索すると、たくさんの業者がヒットします。
費用もピンキリで、安いところであれば5万円~。
高いところだと50万円、100万円するところもあります。
(1−2)クラウドソーシングサイト
企業とフリーランスを結ぶ、「クラウドソーシングサイト」で依頼する方法もあります。
有名どころは、
です。
費用は、制作業者と比較すると安く、約5万円前後で制作してもらえるでしょう。
高くても、10万円くらいが相場のようです。
(2)自作
次に、外注せずに、自分で制作する方法です。
- 「HTML」を使って制作するパターン
- 「ランディングページ制作ツール」を利用するパターン
の2つの方法が、あります。
(2-1)HTML制作
4つの方法の中で、最も難易度の高い方法です。
Web上のプラグラミング言語である、
- HTML
- CSS
を使って、ランディングページを制作します。
Web初心者の場合は、難易度が高いといえるでしょう。
(2−2)ランディングページ制作ツール
スモールビジネスオーナーに、オススメの方法です。
- ペライチ
- WordPressテーマ
- WordPressプラグイン
などを使うことで、ランディングページを作ることができます。
様々なツールがありますので、検索してみると良いでしょう。
成果の出るランディングページに必須の15の要素
「ランディングページを制作する方法が、分かった」
そうしたら、次は構成について、みていきましょう。
「成果の出る、ランディングページにする」
そのためには、構成がとても大切になっていきます。
全部で、以下の15の要素があります。
- ヘッダー
- 共感
- 先入観
- 反論
- 反論の説明
- プロフィール
- 商品紹介
- ベネフィットリスト
- 商品を提供する理由
- 価格の案内
- 保証の案内
- 特典
- 絞り込み
- よくある質問
- 追伸
今回は、各要素について概要をまとめます。
詳しくは、以下の記事をご確認ください。

(1)ヘッダー
ランディングページに訪れたユーザーが、一番最初に目にする部分です。
専門用語で「ファーストビュー」と言われたりします。
このヘッダー部分で、ユーザーはページを読むか読まないかを決めます。
その時間が3秒程であることから、よく「3秒ルール」と言われたりします。
3秒を乗り越えるために大切なのは、適切な「キャッチコピー」と「ヘッダー画像」です。
ユーザーに、響くものを使用しましょう。
(2)共感
ファーストビューで、ヘッダーをみたユーザーが次に目にするのが、この部分です。
「この先を読み進めたい!」と思ってもらうことが、役割です。
そのためにはユーザーに、「共感」してもらう必要があります。
「よく分かってるな~」
と感じてもらうことで、自分事として捉えてもらうことができます。
(3)先入観
ユーザーが抱いている「先入観」を、ここで伝えます。
案内するものが、
- メルマガであれ
- 商品・サービスであれ
この先入観と異なるものでないと、ユーザーは興味を持ってくれません。
上手に伝えることで、のちほど伝える、
- 自社独自のもの
- 自社独自の情報
について、関心を持って、聞いてもらうための布石となります。
(4)反論
伝えた「先入観」を、「反論」します。
ページの中で、最も重要な部分です。
この「先入観の反論」が適したものであれば、ユーザーは興味を持ってくれます。
「えー!?」と思ってもらえれば、最後まで読んでくれるようになります。
(5)反論の説明
「先入観」を「反論」したあとは、その根拠を説明します。
この部分が無ければ、ただ興味を引いただけで終わってしまいます。
きちんと説明することで、ユーザーは驚きと共に「納得」をします。
(6)プロフィール
ここまでの話で、ユーザーに信頼をしてもらってから、初めて自己紹介をします。
なぜなら、いきなり自己紹介をされても、ユーザーは全然興味が無いからです。
「まずは興味を持ってもらう」→「自己紹介」が、正しい順番です。
(7)商品紹介
「自分に関係のある話」で、「聞く価値のある情報」だと判断してもらいました。
「自己紹介」をして、「信頼するに足る」と評価をしてもらいました。
この段階であれば、商品の話を聞いてくれます。
シンプルに、今回のご案内を伝えましょう。
(8)ベネフィットリスト
ベネフィットとは、
「メリットがあることで、どんな良いことがあるか」
ということです。
たとえば、
- 「体重が減る」は、メリット
- 「彼氏が喜ぶ」は、ベネフィット
になります。
ユーザーが、商品紹介をじっくり読まない
だとしても、サラッと理解できるように、お手伝いをしてあげましょう。
(9)商品を提供する理由
商品の紹介とベネフィットを紹介した後は、「提供する理由」を説明します。
今の時代というのは、「モノ余り」の時代です。
ユーザーは、「何」を買うかよりも、「誰」から買うかを大切にしています。
商品の紹介だけでなく、提供する理由も伝える。
そうすることで、あなたやあなたの会社に共感してもらえるようになります。
(10)価格の案内
商品を提供する理由を伝えた後に、「価格」の案内をします。
「価格」で勝負する大企業の場合は、別です。
ですが、スモールビジネスの場合は、きちんと価格設定の理由を伝えましょう。
納得する価格設定の理由を伝えることで、ユーザーは「価格」が気にならなくなります。
(11)保証の案内
しっかりと、価格設定の理由を設定した。
だとしても、ユーザーというのは、やはり不安が残るものです。
その不安を取り除いてあげる、「保証」をご案内しましょう。
商品やサービスに自信があるなら、保証を付けても大丈夫なはずです。
もし、保証ができないようであれば、案内自体を考え直す必要があるでしょう。
(12)特典
「特典」は、ユーザーに「何としても、お申込みしてもらう」ためではありません。
また、「お得感を感じてもらって、特典買い」を期待するものでもありません。
ユーザーへの、「申し込みする理由・言い訳」のプレゼントです。
最後まで、ユーザーに寄り添ってあげましょう。
(13)絞り込み
一通りのご案内を伝えた後は、「ユーザーの絞り込み」をおこないます。
これは、不要なクレームや過剰な約束(オーバープロミス)を避けるためのものです。
- 提供できるもの
- 提供できないもの
両者を、きちんと分けることで、「誠実さ」を伝えましょう。
(14)よくある質問
ランディングページは、良くも悪くも「双方向性」に欠けます。
実際に会って話せば出てくる質問も、ページ上では受け取ることができません。
- 想定される質問
- これまで聞かれたことのある質問
にまとめて答えてあげることで、ユーザーの不安を払拭してあげましょう。
(15)追伸
最後は、「追伸」です。
実は、ファーストビューのヘッダーの次に、よく読まれる部分です。
- 途中を読み飛ばしたユーザー
- いきなり「追伸」を読むユーザー
に向けて、ページのまとめを伝えましょう。
追伸を読んで、もう一度本文を読んでくれることが理想です。
ランディングページを修正する6つの改善・分析ポイント
ランディングページは、「制作して終わり」ではありません。
むしろ、そこからがスタートとなります。
成果の出るランディングページとするには、どのように改善・分析していけばいいのか。
- ABテストの重要性
- ファーストビューの改善
- ターゲットを指定しているか
- キャッチコピーは興味を引くものになっているか
- ベネフィットは伝わっているか
- オファーの改善
6つの改善・分析ポイントを抑えましょう。
(1)ABテストの重要性
ABテストとは、2パターン以上の要素で、比較する手法のことをいいます。
(ABだからといって、2つだけとは限りません)
「ABテスト」の重要性は、どれだけ伝えても伝え過ぎることはありません。
これは、ランディングページに限りません。
なぜなら、
「ABテストさえしていれば、必ず成果の出るランディングページとなる」
からです。
シミュレーションしてみる
たとえば、コンバージョン率が、「1%」のランディングページがあるとします。
ある要素を変更したことで、「1.1%」と「1%」のランディングページとなりました。
そうすれば、次は「1.1%」のランディングページをABテストします。
次は、「1.3%」と「0.9%」になりました。
お分かりですね。
次は、「1.3%」のランディングページをABテストします。
これを繰り返していけば、必ず成果の出るランディングページとなります。
「比較」と「修正」
もちろん、毎回毎回コンバージョン率が、アップするわけではありません。
でも、「比較して修正」をすることはできます。
この「比較」と「修正」というのが、とても大切です。
パターンが1つしかなければ、「比較」することができません。
比較することができなければ、「修正」することもできません。
ですから、必ずランディングページを制作する際には、2パターン用意してください。
ABテストさえ繰り返していけば、必ず成果の出るランディングページとなります。
(2)ファーストビューの改善
ファーストビューは、ユーザーが、ページを訪れた際に一番はじめに目にする部分です。
ここで興味を持ってくれない限りは、その先を読み進めてくれることはありません。
「3秒の壁」を、いかに超えるかが大切なわけです。
このファーストビューを改善するにあたっては、以下の3点をチェックしてみてください。
- ターゲットを指定しているか
- キャッチコピーは興味を引くものになっているか
- ベネフィットは伝わっているか
(3)ターゲットを指定しているか
ユーザーは、
「自分のことだ!」
と思わない限りは、関心を持ってページを見ようとはしません。
なぜなら、「他にもやることは、たくさんあるから」です。
ページを読もうとして、ランディングページに訪れるユーザーは、まずいないのです。
自分のことだ!
そんな中、ページを読んでもらうにはどうすればいいか?
ズバリ、「ターゲットを指定すること」です。
ユーザーに「自分のことだ!」と思ってもらう。
それくらい、指定することをオススメします。
(4)キャッチコピーは興味を引くものになっているか
キャッチコピーが、ユーザーの興味を引くものになっているかを確認してください。
- 「お!なんだ?」
- 「これは役に立ちそうだ」
など、ユーザーの感情を刺激してあげないと「3秒の壁」は超えられません。
現代のユーザーというのは、テレビをはじめとしたメディアからの情報に慣れています。
ですので、ちょっとやそっとの表現では、感情が動きません。
少しでも、心が動けばいい
といっても、情報商材のように過剰にあおる必要はありません。
キャッチコピーを見たユーザーの心が、少しでも動けば良いのです。
そうすれば、興味を持ってくれます。
少しも感情が動かないようなキャッチコピーであれば、黄色信号です。
それはユーザーにとって、「退屈」という感情に結びついてしまうからです。
「これを読んだら、どんな感情になるかな?」
と考えながら、キャッチコピーの修正をしてみてください。
(5)ベネフィットは伝わっているか
ベネフィットは、「メリット」とは異なります。
メリットをただ伝えるだけでは、ユーザーはその価値を理解することができません。
前述のように、
- 体重が減る=メリット
- 彼氏が喜ぶ=ベネフィット
です。
ユーザーの未来を先回りする。
そして、メリットを受けた後に得られるベネフィットを伝えてあげる。
このようにしてみてください。
それこそが、本当の「価値」です。
(6)オファーの改善
オファーとは、「提案」のことです。
要するに「商品・サービスそのもの」やそれに「付随する特典や保証」のことです。
- ABテストを繰り返しても
- ファーストビューを改善しても
ウンともスンとも言わなかった、ランディングページ。
それが、
「オファーを変えた途端に、一気に成果が出るようになった」
ということは、よくあることです。
テクニックも、大切ではあります。
ですが、時には根本からガラッと変えてしまう「大英断」も必要です。
「ランディングページは、コンセプトが9割」とも言われます。
修正を繰り返しても、なかなか成果が出ない場合は、オファーを変えてみてください。
書籍を参考にしてみても、良いかもしれませんね。
編集後記
- ランディングページとは?
- 3つの種類のランディングページを把握する
- なぜランディングページを制作する必要があるのか?
- ランディングページを制作する4つの方法
- 成果の出るランディングページに必須の15の要素
- ランディングページを修正する6つの改善・分析ポイント
についてお伝えさせて頂きました。
- Google広告
- Yahoo!広告
- Facebook広告
- …etc
で集客するにしても、
- ブログ
- YouTube
- 各種SNS
で集客するにしても、ランディングページは必須です。
ランディングページの役割を理解して、制作後は改善を繰り返していってください。
ランディングページを基点に、ウェブ集客に取り組む。
そうすることで、あなたの商売が繁盛することでしょう。