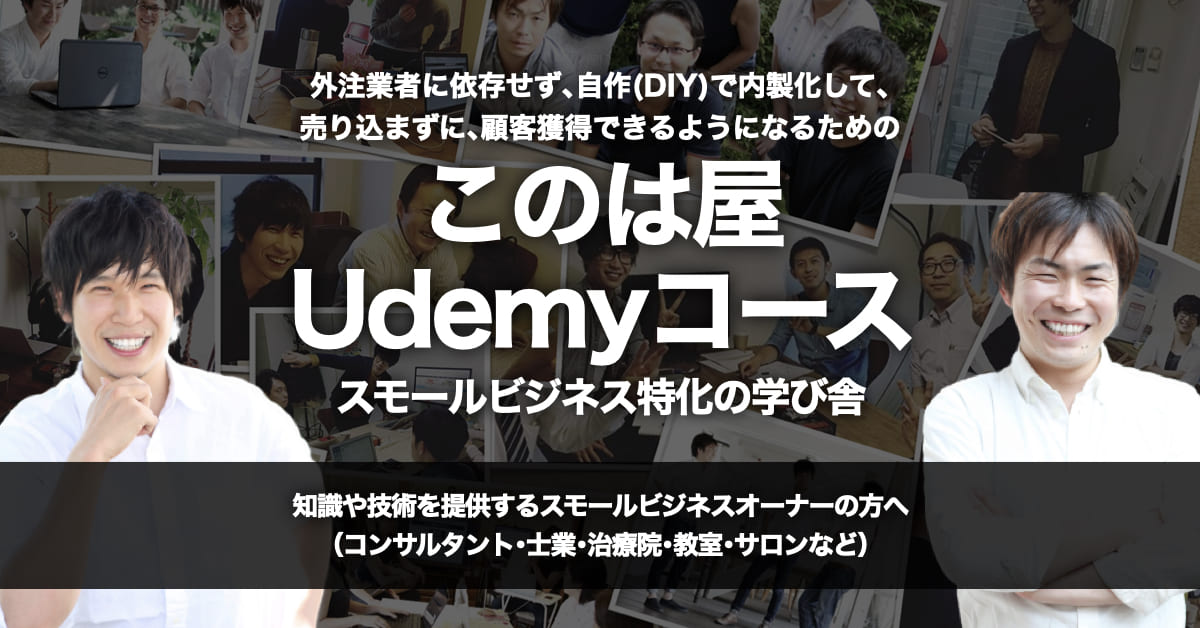「本好きのスタッフが選ぶ、今月のおすすめ書籍ピックアップ」
本屋に行くと、よく目にする宣伝文句です。
手垢のついた表現ではありますが、、、
こうした「おすすめ」コーナーの本は、よく売れます。
「おすすめ」は選びやすい
理由は単純です。
「おすすめ」されているから、でしょう。
本屋に行けば、膨大な数の本が並んでいます。
予め買う本が決まっているのであれば、選ぶのは簡単です。
ところが、買う本がいまいち決まっていないとしたら、どうでしょう。
「おすすめ」の本が、気になるのではないでしょうか。
一番人気
「一番人気」や「売れてます」も同様ですね。
皆が選んでいる。となれば、選びやすいでしょう。
心理学でも、
- バンドワゴン効果
- 社会的証明
と、解説されています。
自分の考えだけで決めるのは、不安なのかもしれませんね。
「みんなも選んでいる」というのは、強烈なメッセージとなります。
本屋に限った話ではない
こういったことは、なにも本屋には限りませんね。
- レストラン
- カフェ
- 英会話スクール
- ネイルサロン
- ウェブサービス
- …ect
などでもそうです。
初めから、「これがいい」という腹積もりがあれば、選ぶのは簡単です。
一方で、明確に決まっていない、という日も必ずあります。
そんな時は、「選ぶ」という手間が生じますね。
「選ぶ」という手間
人は基本的に、選択肢がありすぎると、選べなくなります。
「この20個のメニューから選んでください」
と言われたら、迷いますよね。
量も多いし、どれが自分にあっているかもわからない。
でも、失敗・後悔はしたくない。
こんな状態では、購買意欲も削がれていってしまいます。
そんな時は、「これが良いですよ」のような、選ぶ基準があると、助かります。
このあたりは、書籍を参考にしても良いかもしれません。
代わりに選んであげる
- 本好きのスタッフが選ぶ今月のおすすめ書籍
- シェフのおまかせコース
- 初心者向け、おすすめレッスン
- まずはこれ!初回セット
これらは、「あなたの代わりに選んであげました」というメッセージです。
そのメッセージを参考に、お客さんは商品・サービスを購入するわけですね。
何度も言いますが、選ぶのは面倒なのです。
だからこそ、こちらから選びやすい状況を作り出すことが重要になります。
これは、スモールビジネスでも、そのまま使える方法です。
「おすすめ商品」を作る
もしあなたが、複数の商品やメニューをお持ちの場合。
「おすすめ商品」を作って、提案してみましょう。
- 初心者には、この商品
- こんな悩みを持つ人には、このメニュー
- 経験者には、このコースが安心
というように、対象を分けたおすすめ品を作ると、もっと効果的ですね。
基準を教える
「こんな人は、これがいいですよ〜」
という感じで、選ぶ基準を伝える。
そうすれば、「専門家ポジション」を築くことができます。
直接、ゴリ押しのセールスすると、お客さんは逃げてしまいます。
売るのではなく、教えてあげれば良いのです。
- 正しい選び方
- チェックするべきポイント
- よくある失敗
- 良し悪しを見分けるコツ
- …etc
このように、「判断基準」を伝えるのです。
売るよりも、選んでもらう
判断基準を伝えたら、あとは簡単。
選んでもらうだけです。
基準はすべて伝えました。あとは、あなたが選んでください。
このような感じで、相手に判断を委ねる。
1つの商品を強引に勧めるよりも、複数の選択肢から、ニュートラルに提案する。
逆説的ですが、人は、自分に最適なものを、自ら選びたいのです。
編集後記
集客・販売につなげるためには、「簡潔さ」が欠かせません。
複雑でノイズの多い状態では、商品は売れません。
選択するという行為は、疲れるものです。
こちらが基準を示し、選んであげた上で、提案してみましょう。